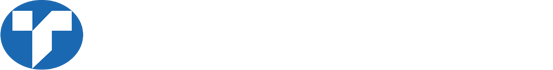Entry & My Page
Entry & My Page
Project Story
明日のための
モノづくり
Prologue
プロローグ
近年、コンテナ船の大型化や船社間の連携による基幹航路の再編など、海運・港湾を取り巻く環境は大きく変化しつつある。そうした中、基幹航路に就航する大型船の入港や、増加するコンテナ貨物の取り扱いに適切に対応し、我が国に寄港する基幹航路の維持・拡大を図るため、現在横浜港においてコンテナターミナルの再編整備が進められている。これは横浜港の新本牧ふ頭地区にて、約140haの埋め立てを実施する一大プロジェクトだ。その中で東洋建設は、臨海部物流拠点を形成する事業のうち、将来、臨海幹線道路となる、A護岸築造工事を担当した。ベテラン作業所長と若手メンバーで形成されたチームに、それぞれの取り組みを語り合ってもらった。
Member
メンバー
-

土木
1989年入社
大槻 貴志
所属
関東支店 土木部
新本牧A築造作業所 所長出身
工学部 土木工学科卒
-

土木
2017年入社
南部 拓歩
所属
関東支店 土木部
新本牧A築造作業所 現場代理人出身
創造理工学部 社会環境工学科卒
-

土木
2020年入社
佐藤 拓実
所属
関東支店 土木部
新本牧A築造作業所出身
創造工学部 都市環境工学科卒
-

土木
2022年入社
大平 賢也
所属
関東支店 土木部
新本牧A築造作業所出身
工学部 環境土木工学科卒
-

土木
2023年入社
加谷 真悟
所属
関東支店 土木部
新本牧A築造作業所出身
創造工学部 都市環境工学専攻修了

Episode 01
コンテナターミナル再編の一角を担う現場に、
若手を中心としたメンバーが結集した。
最初にプロジェクトの背景と経緯を教えてください。
大槻
「横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業」と呼ばれる大規模なプロジェクトです。横浜港は、日本の国際貿易の窓口として重要な拠点ですが、今後増加が見込まれるコンテナ貨物量に対し、取り扱い能力の不足が懸念されています。貨物量増大やコンテナ船の大型化などに対応し、横浜港を国際コンテナ戦略港湾として、コンテナ貨物の取扱い機能を量・質の両面でさらに強化するため、コンテナふ頭の再編・強化や先進的な施設整備を進めること。これがプロジェクトの目的です。
南部
その中で私たちが取り組んでいるのが、新本牧地区護岸(防波)A築造工事です。プロジェクトの中核を担う施設として、大水深・高規格コンテナターミナルと物流施設を一体化した臨海部物流拠点の整備が計画されています。この拠点整備において将来的に臨港幹線道路となるのが、今回取り組んだA護岸築造工事でした。
大槻
「護岸築造」とはどんな工事なのかをまず説明します。護岸工事とは、防波堤や防潮堤の築造やそれらの補強工事を指します。そして護岸築造に不可欠なのが、「ケーソン」と呼ばれる鉄筋コンクリートで作った大きな函です。波を防ぐ防波堤や船を停泊させるための岸壁などに使用されるものです。このケーソン製作を担当したのが、佐藤さんでした。
佐藤
これまで経験してきたのは、耐震補強工事や護岸改修工事など、比較的コンパクトな現場でした。今回のような大型プロジェクトに配属されたことがなかったため、当初は期待よりも不安の方が大きかったですね。しかもミッションは、護岸築造の要となるケーソン製作。経験がなかったことに加え、ケーソン製作ヤード※1のジョイントベンチャー(JV)の現場は、当初は東洋建設の社員は私一人だったので、不安一色になったことを覚えています。所長や南部さんのサポートでなんとか前に進めることができました。 ※作業場
大平
私は今回が2件目の現場になります。最初の現場は陸上土木でしたから、海洋土木は初めて。現場に入るのが楽しみで、ワクワクしていました。また、難しく大変な工事と知らされていたので、自分ができることをまっとうしようと現場に入りました。そして私の役割の一つとなったのが「BIM/CIM」の担当です。社内では活用が進んでいますが、私は未経験。一から勉強して取り組みました。
加谷
私は入社して、最初に入った現場がこのプロジェクトです。現場経験がありませんから、どのような人がいて、どのような仕事をするのか、ついていけるだろうか、自分の居場所をつくれるだろうか等、とても不安でした。現場に入ると先輩方はもちろん、JVのメンバーや協力会社の方々も、みんな優しく、人が良く、すぐに不安は解消されました。とにかく勉強すること、何でも吸収することを心掛けました。
大槻
私以外は、すべて20歳代という若いチームとなりました。当社にとって若手育成は大きなテーマで、そのためにも彼らにさまざまな現場や工種を経験してもらうことが必要だと考えています。その意味で、今回のプロジェクトは、皆にとって貴重な経験になったと思いますね。

横浜港を国際コンテナ戦略港湾としてさらに強化するための横浜港国際海上コンテナターミナル再整備事業。その社会的使命は非常に大きいものがある。

所長の大槻以外はすべて20代で構成されたプロジェクトメンバー。それぞれの役割を果たしながらプロジェクトは進んでいった。

Episode 02
「ケーソン」製作と大型起重機船によるえい航。
「BIM/CIM」を用いた新しい施工管理のカタチ。
プロジェクトの流れを教えてください。
大槻
護岸築造は端的に言えば、製作されたケーソンを海上に据え付ける工事ですが、据え付けに至るまでは、さまざまな工程があります。はじまりは、佐藤さんが担当したケーソン製作でしたね。
佐藤
通常ケーソンは、据え付ける場所の近くで、場所を確保し製作されます。しかし今回指定された製作ヤードは千葉県袖ケ浦でした。新本牧の現場からは、東京湾を挟んでちょうど反対側にあるため、起重機船でえい航する必要があるのが難しい点でした。製作したのは18m×9m×13.5m(およそ1600t)のケーソンが6函、20m×10m×10.5mのケーソンが2函。私は施工管理として協力会社とともにケーソン製作を担当しました。ケーソンはコンクリート打設によって製作されますが、必要な打設回数は計46回。現場へのえい航日が決まっている中で、荒天などを考慮した工程を組み、なんとか製作を進めていきました。
南部
私は新本牧からサポートしていましたが、工程の遅れは許されない状況でしたから、製作中は常に緊張の中にありましたね。期日通りに製作を終えるだけでなく、据え付けに向けた準備作業も考慮する必要がありますし、出来形や品質において問題はないかどうか、心配は尽きませんでしたが、佐藤さんがしっかり結果を出してくれ、無事に吊り出し日を迎えることができました。加谷さんも途中からケーソン製作の応援に入ってもらいましたね。
加谷
私は佐藤さんから指示されたことにひたむきに取り組みました。佐藤さんの動きを見て施工管理のあり方を学ぶ一方、現場掲示物の掲示や危険個所の喚起、工事状況の写真の撮影などを担当しました。最初の現場がケーソン製作であり、吊り出し日はそのスケールの大きさに感動しました。
佐藤
そうですね。3000t吊の大型起重機船でコンクリート重量物であるケーソンを吊り上げたまま、千葉から横浜港までえい航しました。なかなか見られない光景で、マリコンだからこそ味わえる醍醐味だなと思います。

現場から東京湾を挟んだ千葉県で製作されたケーソン。地上にある自動車と比較するとそのスケールの大きさは一目瞭然だ。ここから現場へとえい航していく。

3000t吊の大型起重機船で巨大なケーソンを吊り上げたまま、現場へえい航する。マリコンである東洋建設でも滅多に見られないスケールの大きな仕事だ。
大槻
ケーソン製作と同時進行で、据え付け場所で行ったのが基礎捨石投入でした。波を受け止めるケーソンの土台部分となる捨石を基礎地盤に投入してケーソンの安定を図るのが目的です。またケーソンの荷重を分散する役割も担います。安定した土台とするため、これらの捨石を平らに並べ替えする「均し(ならし)」作業を潜水士によって行い、工事のハイライトともいうべきケーソン据え付けを、2023年9月から2カ月にわたって行いました。その後、据え付けたケーソン上部にコンクリートで蓋をし、護岸の安定を図る裏込石を投入、これが一連の護岸築造の流れです。この工程を管理する中で、大平さんが「BIM/CIM」担当となりました。
大平
はい。「BIM/CIM」は、3Dモデルを作成し施工に活用する取り組みです。たとえば、基礎工や裏込工に先立って、計測結果から得られたデータを用いて、地形モデルを作成しました。また構造物や配筋モデルを作成することで、ケーソン製作のサポートも行っています。捨石・裏込石の投入検討や数量算出、ケーソン据え付け計画等でも、CIMモデルを活用しました。すべて初めてのことでしたが、事前に3Dモデルがあることで、現場施工がスムーズに進むなど、新たなノウハウを得られましたね。
南部
私は、現場代理人として初めての現場でした。期待感と不安感が入り交じりながらの着任でしたが、現場運営をリードする責任感を持って行動しようと現場に臨みました。施工管理全般に加えて、発注者対応も重要な役割でした。書類作成や関係各所への申請書類等、日々書類作成に追われる部分が多かったですが、各工種が常に輻輳して進行するため、工程調整や施工検討、他工区との調整等に細心の注意を払って、現場を進めました。

Episode 03
難題をクリアしたケーソン据え付け工事。
同時に、ICTを活用した先進的な工法を導入した。
技術的なハードル、今回のプロジェクトの特徴を教えてください。
大槻
何と言っても、千葉から横浜港まで大型起重機船でケーソンを吊り上げたままえい航する試みが大きなハードルでした。メンバー全員が緊張感の中にあったと思います。東京湾は非常に多くの船舶が航行していますから、仮に一般船舶との衝突事故等が発生すれば、プロジェクト自体が停滞してしまいます。関係各所への事前説明、周知を徹底し、事故なく据え付け場所までえい航できたことに大きな安堵感を覚えましたね。
南部
同感です。ただ据え付け自体も大変でしたね。担当工区以外で、当社のケーソンと接続が必要な護岸がすでに築造されており、極めて狭隘(きょうあい)な海域でケーソンを据え付ける必要があったからです。その海域での大型起重機船の作業は困難だったためケーソンを浮かべて水を注入し、据え付ける方法で作業を進めました。綿密な施工計画と細心の注意を払い、正確に据え付けることができたときは、本当にホッとしました。
大槻
ケーソンのえい航、据え付けという大きなハードルを乗り越えたことで、それ以降、工事は円滑に進められました。また今回の工事では、施工管理に「BIM/CIM」を積極的に活用したことも大きな特徴の一つです。大平さんが担当した「BIM/CIM」の取り組みですね。
大平
「BIM/CIM」の活用は、建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を実現する「i-Construction」の一環です。実際、自分で3Dモデルを作成し現場で活用する中で生産性が格段に変わることを実感し、これからの海洋土木に必要とされる技術だと感じました。今後も、「BIM/CIM」の知見を深めていきたいと思っています。
南部
「BIM/CIM」に加えて、ICT活用の取り組みも、今回のプロジェクトの特徴の一つでしたね。基礎捨石均しやケーソン据え付けなど潜水士が海中で行う作業が多く発生するのですが、それらを可視化して効率と安全性を高めるものです。潜水士がダイバーカメラを装着してリアルタイムに映像を送信し、船上に配置したモニターで潜水作業を監視するシステムや、ダイビングコンピュータ(ダイバーウォッチ)を装着して、それらから得たデータによって潜水時間の管理を行い、潜水士の安全性の向上を図る取り組みなども進めました。またGNSS(衛星測位システム)を利用して所定の位置にケーソンを誘導するシステムを使用しました。こうしたICT施工の効果が今後検証されていくことになると思います。
佐藤
他にも魅力的だなと思ったのが、「生物共生護岸」の適用です。これはケーソン壁面やケーソン前面に生物の生育に配慮したコンクリートパネルと生物共生ブロックの製作・設置を行ったものです。これらには、低炭素型材料を活用したコンクリートが使用されていて、社会貢献につながる取り組みに参加できたことは誇らしいです。
加谷
私は初めての現場で、こうした先進的な取り組みに携わることができました。毎日勉強しながら働くことの充実感を、この現場で得ることができたと思っています。

狭隘な海域で据え付ける必要があったこの現場では、ケーソンを浮かべて水を注入し、据え付ける方法が採用された。綿密な施工計画のもと正確に据え付けが成功したときが、一同がホッとした瞬間だ。

BIM/CIMや、潜水士の作業をリアルタイムで監視するシステム、iPhoneを使った現場の出来形管理など、ICT施工も積極的に取り入れられた。

Episode 04
やりがい、達成感、楽しさと喜びを実感できた、
日本の経済・産業を支える一助となるプロジェクト。
やりがいや今後の目標などを教えてください。
南部
今回のプロジェクトはさまざまな工種が混在する大規模工事でした。そのため難しさや厳しさもありましたが、工事が一歩一歩進んでいくことに改めて喜びと達成感を感じましたね。現場代理人という責任ある立場に立ったことで、一層そのことを実感します。また若いメンバーで構成されていたので、風通しが良く、働きやすさも感じました。
佐藤
今回はケーソン製作という大切な工程を任され、自分のような若手でも裁量をもって働けることを実感しました。そして、自分が担当した構造物がカタチに残り、地域の人々の暮らしの役に立つこと、そこにも大きなやりがいを感じます。
大平
私は「BIM/CIM」を担当していただけでなく、ケーソン据え付けなどで、現場の出来形等の管理も行っていました。何もなかった現場にケーソンを据え付け、どんどん景色が変わっていくのを見て、ものづくりの楽しさ、面白さを全身で感じられた現場でした。
加谷
私はケーソン製作の最終フェーズが印象深いです。型枠が取れ、足場を外し、真っ白で巨大なケーソンが現れたとき、本当に感動しましたし、達成感がありました。皆でつくったケーソンだと感慨深かったです。

若手メンバーにとってこの現場の経験がそれぞれの成長につながるとともに、若手の成長が東洋建設そのものの成長にもつながっていく。
南部
今後は今回の経験を後輩に伝えていくとともに、自身が所長として現場の施工管理に従事できるよう努力していきたいと考えています。
佐藤
この現場では大型構造物の製作、鉄筋コンクリートについて学ぶことができました。この知見を活かして、ケーソン据え付けなどの大型工事に取り組んでいきたいと考えています。
加谷
私にとっては今回の現場が施工管理としての出発点。まだまだ吸収すべきことが山積しています。日々学ぶ中で成長し、将来は大きな仕事を任せられるような人材に成長したいと思っています。
大平
今回学んだ「BIM/CIM」は自身にとって大きな財産です。今後も「BIM/CIM」を活用した現場に携わり、さらにその世界を究めていきたいと思っています。一方、施工管理としてあらゆる工種に対応できる人材になりたい。「BIM/CIM」×施工管理のスキル・技術をこれからも磨いていきたいですね。
大槻
今回のプロジェクトは、横浜港が国際コンテナ戦略港湾として国際競争力を強化し、日本の経済・産業を支えていく、その一助になるものでした。その社会的意義、社会貢献の高さを、みんなには改めて感じてほしいと思います。私自身も、今後こうした経験を若手に伝え、若手の成長を支援していきたいと考えています。

今回の新本牧地区護岸A築造工事は、「横浜港国際海上コンテナターミナル再編整備事業」の一角を担ったが、再編整備事業は今後も続いていく。この海面がほぼ埋め立てられるという国家的プロジェクトだ。
Recommended
Contents